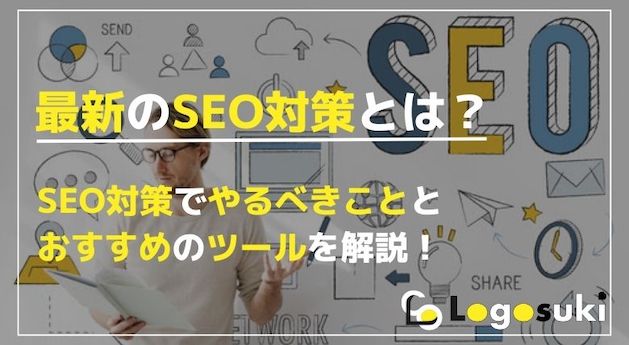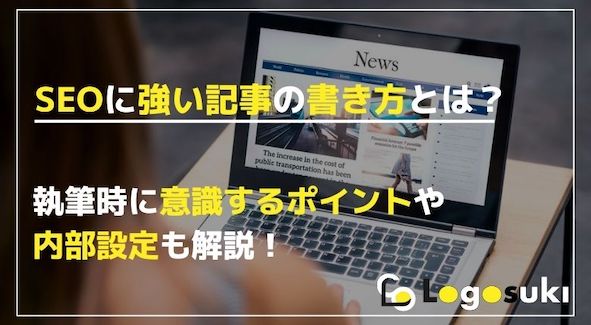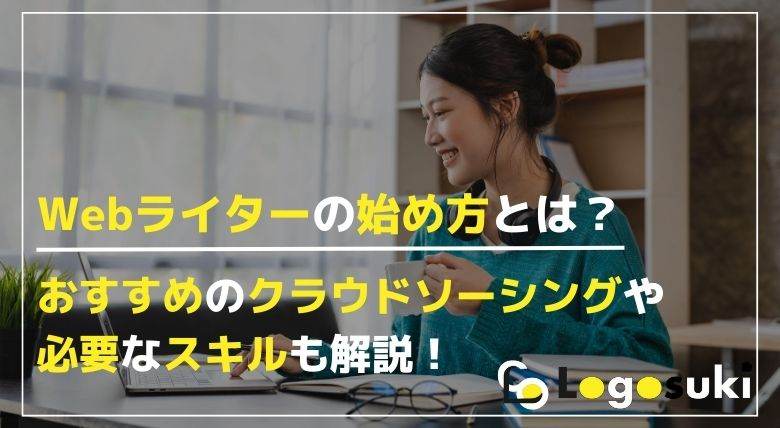Web上にサイトやコンテンツを発信している方であれば、一度は「SEO」という言葉を耳にした経験があるのではないでしょうか?
多くのユーザーにサイトやコンテンツを知ってもらうには、検索結果で上位表示を目指す「SEO記事」の執筆が重要です。
この記事では、SEO記事について、次の4つを解説します。
- SEOで評価される記事の特徴
- SEOで評価されない記事の特徴
- SEOで評価される記事を書くコツ
- SEO記事執筆で使えるツール
この記事でSEOに関する理解を深め、検索上位に記事を表示させましょう。
【そもそも】SEO記事とは?
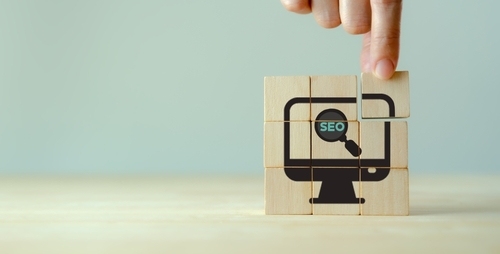
SEO記事とは、GoogleやYahooといった検索エンジンで検索した時に、上位に表示されることを目指して書かれた記事です。
多くのユーザーが上記のGoogleやYahooで調べ物をするため、検索で上位に載せられると、自社サイトやコンテンツの記事に多くのユーザーを集められます。
参考:Google for Developers「Google公式 SEOスターターガイド」
評価されているSEO記事は「検索の上位に上がっている記事」
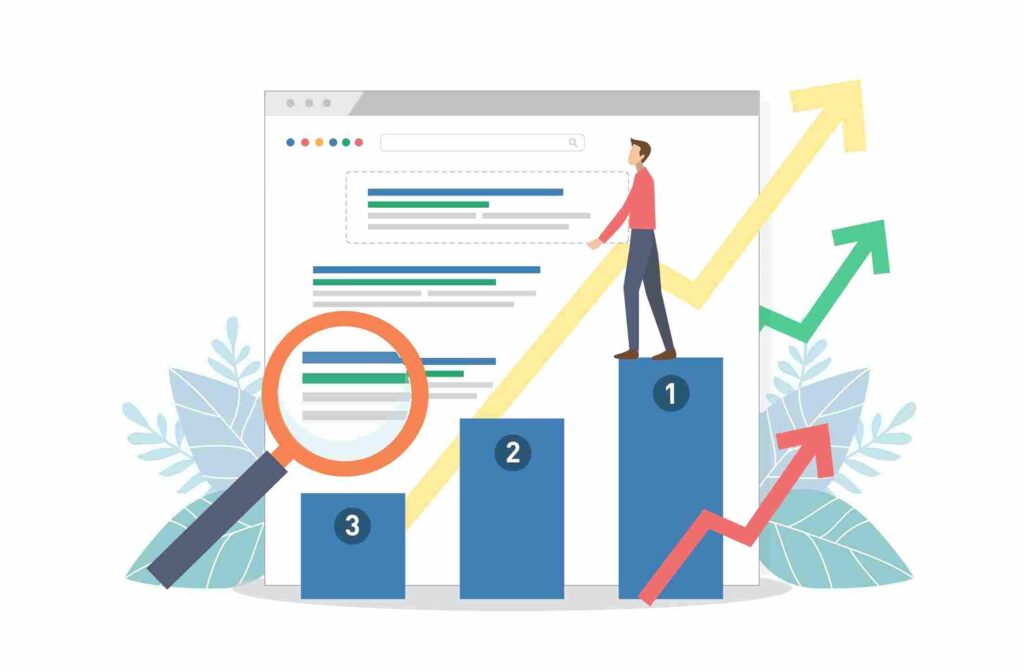
冒頭で紹介しましたが、評価されている記事は、検索の上位に上がっている記事を指します。
上位表示されている記事は、Googleのアルゴリズムで評価され「ユーザーに有益」と判断されているためです。
一般的に、私たちはスマートフォンやパソコンで検索を行う場合、検索結果の1ページ目のトップに出ているコンテンツを見る傾向があります。
Googleも、検索結果の1ページ目に上がるコンテンツをユーザーが見る傾向があると認識しています。
そのため、Googleが高く評価したコンテンツが上位にきていると判断できるのです。
SEOで評価される記事の特徴3つ

ここでは、具体的にSEOで評価される記事の特徴を紹介します。
Googleのアルゴリズム(評価判定システム)によって評価されますが、評価される記事には主に次の3つの特徴があげられます。
- 記事のコンテンツ(内容)が高評価を得ている
- 被リンクで高評価を得ている(他記事に記事が掲載される)
- googleのポリシーに従っていて高評価を得ている
①記事のコンテンツそのものが高評価を得ている
ユーザーが知りたいことや求めている情報に、きちんと応えているコンテンツが評価を得ます。
例えば「美味しい麻婆豆腐のお店」が知りたいにもかかわらず「美味しい麻婆豆腐の作り方」が紹介されていたら、求めている情報を提供できていません。
つまり、ユーザーが検索窓で検索するキーワードから、ユーザーが求めている情報を推測して、きちんと応えられているページは評価されます。
記事を読んでいる最中に新たに生まれる疑問に対しても、情報提供できていると、さらに高評価を狙えます。
②被リンクで高評価を得ている(他記事に記事が掲載される)
被リンクによってSEO記事の評価が上がります。
被リンクとは「外部Webサイトが自社コンテンツのリンクを貼っている」ケースです。
SEO記事評価をアップさせるために有効な被リンクには、次の2つがあります。
- 被リンクされているコンテンツの持ち主(サイト自体)が高評価
- 評価の高いコンテンツ(ページ)から被リンクされる
もともと上位に入るようなサイトやコンテンツから、被リンクをもらえると自身のページの評価も底上げされるのです。
③Googleのポリシーに従っていて高評価を得ている
Google公式見解のGoogle for Developersは、Google検索の表示に最も影響が大きい対策は次のものと明示しています。
引用:Google for Developers「Google検索の基本事項」
- 有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツを作成する。
- ユーザーがコンテンツを検索するときに使われる可能性のある単語を選んで、これらの単語をページ上の目立つ場所(ページのタイトル、メインの見出しなど)や、わかりやすい場所(代替テキスト、リンクテキストなど)に配置する。
- リンクをクロール可能にする。これにより、Google がページ上のリンクを使ってサイト内の他のページを検出できます。
- サイトに関する情報を発信する。自分のサイトで紹介しているサービスや製品について、同じような志向の人々と交流できるコミュニティに参加しましょう。
- 画像、動画、構造化データ、JavaScript などの他のコンテンツがある場合、各タイプに固有のベスト プラクティスを実践する。これにより、ページ上の各コンテンツを Google に提示できます。
- サイトに適した機能を有効にすることで、Google 検索におけるサイトの表示を改善する。
- 検索結果に表示したくないコンテンツがある場合や、完全なオプトアウトを希望する場合は、適切な方法でGoogle 検索でのコンテンツの表示を管理する。
ユーザーに信頼性の高いコンテンツを提供するのはもちろん大事です。
さらに、新規で作成したコンテンツは検索エンジンに気づいてもらい、検索エンジン内に登録してもらうのも重要でしょう。
また、似たようなコンテンツを提供している他サイトのリンクを貼ったり、交流をしたりして、提供コンテンツの専門性の高さを示せるようになります。
SEOで評価されない記事の特徴5つ

反対にSEOで評価されない記事を把握しておくと、評価を下げない対策ができます。
評価を上げることと同様に、評価を下げないのも重要です。
次の5つが評価されにくい記事の特徴です。
以下に注意してコンテンツを作ってみてください。
- 見出しと本文の内容が食い違っている
- ユーザーが求めている情報を得られない
- 情報が古い
- ページの表示に時間がかかる
- 文字のみでさらに長文
①見出しと本文の内容が食い違っている
見出しと本文の内容が異なるコンテンツは、ユーザーからの評価が下がりやすいです。
例えば、見出しが「美味しいカレーの作り方」にもかかわらず、本文の内容は「美味しい東京のカレー屋」だとしたら、ユーザーは混乱します。
そのうえ、ユーザーは「知りたいのは美味しいカレーの作り方なのに…」とすぐにページを離れて、カレーの作り方を説明している別のページに移動してしまうでしょう。
見出しは、お店でいうと看板です。
看板(見出し)と同じ内容のサービスや料理(コンテンツ)を提供しましょう。
②ユーザーが求めている情報を得られない
先ほどの「美味しいカレーの作り方」を例にすると、ユーザーはまずコンテンツを見て「美味しいカレーの作り方」を知ります。
その後、「じゃあ美味しいカレーを作るためのスパイスはどこで買えるのか」と疑問が湧いてくる可能性があります。
または、「じゃあ美味しいカレーに合う米は何か」と考える読者もいるでしょう。
そのため、ページを読みながら浮かんでくるユーザーの疑問を先回りして回答できるコンテンツが作れると、情報に厚みが出ます。
記事にボリュームが出ると、ユーザーの理解度を深められるのです。
ただし、読み手の負担も増えるため、注意が必要でしょう。
そのため、記事の前半でユーザーの求める情報を提示し、徐々に詳細を伝えるのが望ましいです。
③情報が古い
情報が古いページは評価されにくいです。
なぜなら、情報は時代の流れに合わせて変わるためです。
特にITの技術は常に進化をしていて、1年前の情報だと流行についていけません。
古い情報だと、現在の状況とかけ離れた認識のコンテンツになってしまいます。
ジャンルによって変化のスピードは異なりますが、可能な限りニュースや新聞のように新しい情報を更新し続けるのがおすすめです。
④ページの表示に時間がかかる
スマートフォンで動画をみたり、ゲームをしたり、仕事中にパソコンをいじったりしているときに動作が遅いと、もどかしい気分になりますよね。
Webページも同様で、表示に時間がかかるコンテンツはユーザーに不便を感じさせるでしょう。
コンテンツ制作時に動画を入れたり、動きの多い表示をさせたりする場合は特に注意しましょう。
どんなに良いコンテンツを提供できても、動作が遅いとユーザーから見てもらいにくくなります。
⑤文字のみで長文
コンテンツのジャンルによりますが、文字のみで、かつ長文のコンテンツは評価されにくいです。
ユーザーに読む際の抵抗感を与え、スクロールしてもすぐに離脱される恐れがあります。
ユーザーの中には、視覚情報でコンテンツを読み進めたい層が一定数います。
そのため、文字ばかりになる場合は、画像やリストを交えつつ、情報の受け手の負担を減らしましょう。
記事を読み進めていく中でも、画像やリストがあった方が情報が入ってきやすいです。
ただし、あくまで記事を読みやすくするための画像であって、挿入画像の枚数や質によって表示順位があがるわけではありません。
リストもやみくもに入れず、情報を整理するために適切な箇所に入れると効果的です。
SEOで評価される記事を書くための【コツ6つ】

ここからはSEO評価をあげて、表示順位をアップするためのコツを6つ紹介します。
- 記事内容をユーザーの検索意図(欲しい情報)に合わせる
- Googleのポリシーに合わせた記事内容にする
- ユーザーが検索時に入力するワード(対策キーワード)を記事内に入れる
- タグの設定をする
- 画像や表などを入れて読みやすくする
- ファーストビューで読み進められる工夫をする
①記事内容をユーザーの検索意図(欲しい情報)に合わせる
前述しましたが、SEOで評価される記事は、ユーザーが求める情報を提供している記事です。
この「ユーザーが求める情報」が検索意図です。
検索意図を探すときは、ユーザーが何を知りたくて、検索窓にキーワードを打ち込んだのか想像をします。
もちろん、想像だけでは的外れな場合もあります。
想像をした後に、実際に記事で定めようとしているキーワードを検索してみましょう。
すると、定めたキーワードの検索意図を満たすと判断される記事がトップに出てきます。
トップに書いてある記事の内容を参考にすれば、検索意図を満たせる記事が書けるようになります。
ただし、トップの記事の情報はあくまで参考なので、きちんと自分の文章で説明しなくてはいけません。
②Googleのポリシーに合わせた記事内容にする
先ほど紹介したGoogle for Developersの記述に合わせた記事内容にするのが、上位表示の近道です。
Googleで下記がSEO上位表示で大きな影響を及ぼすと述べています。
まず下記に関する対策をしましょう。
引用:Google for Developers「Google検索の基本事項」
- 有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツを作成する。
- ユーザーがコンテンツを検索するときに使われる可能性のある単語を選んで、これらの単語をページ上の目立つ場所(ページのタイトル、メインの見出しなど)や、わかりやすい場所(代替テキスト、リンクテキストなど)に配置する。
- リンクをクロール可能にする。これにより、Google がページ上のリンクを使ってサイト内の他のページを検出できます。
- サイトに関する情報を発信する。自分のサイトで紹介しているサービスや製品について、同じような志向の人々と交流できるコミュニティに参加しましょう。
- 画像、動画、構造化データ、JavaScript などの他のコンテンツがある場合、各タイプに固有のベスト プラクティスを実践する。これにより、ページ上の各コンテンツを Google に提示できます。
- サイトに適した機能を有効にすることで、Google 検索におけるサイトの表示を改善する。
- 検索結果に表示したくないコンテンツがある場合や、完全なオプトアウトを希望する場合は、適切な方法でGoogle 検索でのコンテンツの表示を管理する。
③ユーザーが検索時に入力するワード(対策キーワード)を記事内に入れる
記事内にユーザーが入力するキーワードを入れるのもポイントです。
ユーザーはもとめる情報を調べるときに、キーワードを打ち込みます。
記事内にそのキーワードがないと、知りたい情報が得られているのか不安になったり、自分の求めている情報が不明瞭になったりします。
そのため、キーワードを意識してSEO記事執筆をしましょう。
「あれ?今なんの話している(されている)んだっけ?」状態を防げます。
④タグの設定をする
コンテンツの内容は人間と機械の双方から、きちんと理解できる設計にしましょう。
そのため、Webサイト表示に必要なコードを使用しながら、端的なワードで記事内容を示す必要があります。
次の5つは避けるべきと、Google公式のスターターガイドにも記載されています。
- <title>タグに「無題」や「新しいページ」といった、初期設定のテキストやコンテンツと無関係なテキストを設定する(何を記述している文章か判断できない)
- <title>タグにすべて同じタイトルが入っている
- <title>タグで極端に長い文章や不要なワードを乱立する
- メタディスクリプション(検索結果表示のさいに現れる要約文章)に、キーワードのみを羅列する
- h2やh3タグの文字の大きさを統一しない
上記の5つはGoogleにもユーザーにとっても、内容を把握しにくくなるため避けましょう。
コードの概念をより深く理解したい方は、下記を参考にしてみてください。
参考:アクセス解析ツール「AIアナリスト」 ブログ | SEOに効果的なタグを徹底解説!titleタグ・metaタグからhタグまで
⑤画像や表などを入れて読みやすくする
文章コンテンツ内に、関連した画像や表を入れると、ユーザーが理解しやすくなります。
文章と画像、表にはそれぞれメリットとデメリットがあります。
文章と画像、表を組み合わせるとそれぞれのメリットを活かしあえるのです。
| 表現メディア | メリット | デメリット |
| 文字 | ・何度も読み返せる ・日時や数値を正確に伝えられる ・同音異義語を正しく伝えられる ・情景を文章で伝えられる ・複雑な情報を理解しやすい ・気になる情報だけを取り出しやすい | ・読むのに手間がかかる |
| 静止画 | ・時間をかけて試聴しないですむ ・情報をダイレクトに伝えやすい | ・伝えられる情報に限りがある |
| 動画 | ・大量の情報を視覚、聴覚的に得られる ・音声だけであれば、別のことをしながら情報が得られる | ・気になる情報だけを取り出すのに時間がかかる |
| 表 | ・情報が整理されていて理解しやすい | ・伝えられる情報に限りがある |
⑥ファーストビューで読み進められる工夫をする
コンテンツをみにきた際に、スクロールせずに内容が確認できる部分をファーストビューといいます。
ファーストビューで興味を引く内容が記載されていないと、ユーザーが離脱してしまいます。
離脱を防ぐために、ファーストビューでは次の3つを意識してみましょう。
- 読者の疑問を提示する
- 記事概要を説明する
- 記事を読むと何がわかるのかを明示する
上記3つを意識することで、読者が記事を読む意味を理解し、その先も読みたいと思ってもらえます。
SEO記事作成時は「SXO」を意識することも大事

SEO記事を作成する際は、ユーザーを最優先に考えたコンテンツ作りが重要です。
その考え方をSXOと呼びます。
SXOはSearch Experience Optimization(検索体験最適化)の略です。
つまり検索ユーザーが「コンテンツ内でいかに満足できるか」を指します。
SEOはSearch Engine Optimization「検索エンジン最適化」で、検索エンジンを優先してコンテンツ作りをするため、SEOとSXOは別の考え方とされています。
しかし、Googleのアルゴリズムが時代と共に進化して、より人間のユーザーに近い評価ができるようになっています。
SEOとSXOの境目がなくなってきているため、SXOに注目したユーザー最優先のコンテンツ作りがおすすめです。
ユーザーファーストにするにはユーザーのことを知るリサーチが重要

ユーザーを最優先にしたコンテンツ作りをするには、どんなユーザーに向けて提供するのかを設定しましょう。
ユーザーを設定すると、専門性、表現方法を変えてより伝わりやすいコンテンツ作りができるためです。
ユーザー設定をする際は、1人の特定の人に絞って、その人の特徴をできるだけ詳細に書き出してみましょう。
その詳細に合わせたコンテンツを提供すると「自分に向けられている」と感じ、ユーザーに伝わりやすくなります。
SEO記事を作成時に便利な無料ツール4つ

ここからは、SEO記事の作成時にあると便利な無料ツールを4つご紹介します。
- 画像・イラスト・動画ツール |『Canva』
- キーワード検索ツール |『ラッコキーワード』
- キーワード検索ツール |『ラッコキーワード』
- 校正関連ツール |『CopyContentDetector』(コピペチェッカー)
試しに使ってみて、使い心地が良ければ有料版でさらに細かい作業も可能です。
画像・イラスト・動画ツール |『Canva』
コンテンツ内に使用する画像を探したり、加工したりしたい場合は「Canva」がおすすめです。
無料である程度のサービスが利用できるためです。
Canvaでできることは次の3つです。
- 画像のサイズを調整
- 画像の上に文字を配置
- 画像の明度、サイドの調整
また、Canvaでは名刺やロゴ、チラシの制作もできます。
【Canvaの詳細】
キーワード検索ツール |『ラッコキーワード』
コンテンツで対策するキーワードを検討する際には、「ラッコキーワード」が使用できます。
ラッコキーワードでは、具体的に以下のことを調査できます。
- サジェストキーワード
- 入力KWで上位表示される記事の詳細
- 検索ボリューム(有料)
- 検索流入キーワード(有料)
- 類語・同義語
- 共起語
- 関連語
- 情報をcsvデータとしてダウンロード
キーワード選定は、コンテンツをみてもらえるユーザー獲得に大きな影響があります。
キーワード選定は調査をきちんと行いましょう。
校正関連ツール |『CopyContentDetector』(コピペチェッカー)
記事内の文書がコピペかどうかを調べるツールに「CopyContentDetector」があります。
他のコンテンツをそのまま真似るのはタブーです。
しかし、数えきれないコンテンツが世に出ているため、意図せず被ってしまう文章が出る可能性もあります。
そのため、コピペチェッカーできちんとオリジナルの文章に仕上げましょう。
AIツール | 『ChatGPT』
コンテンツのアイデア出しや、ユーザー調査の足がかりとして「ChatGPT」も有効です。
あるキーワードを入力して調べるユーザーの人物像や、コンテンツ内容自体のアイデア出しのサポートをしてくれます。
もしアイデアが浮かんでこない場合は「ChatGPT」を使ってみるのも1つの手です。
よいSEO記事はユーザーのことを調べて構成された記事

この記事では、SEOで評価される記事の特徴と評価されるためのコツに関して解説しました。
この記事のまとめは以下のとおりです。
- SEOで評価されている記事は次の3つの特徴がある
ユーザーから高評価を得ている記事
他サイトから被リンクされる記事
Googleのポリシーに沿った記事 - SEOで評価される記事を書くコツはユーザーとエンジン双方にわかりやすい記事
- ユーザーの優先度が高い記事はSEOからの評価も受けやすい
- ユーザーを調べるのが重要
ユーザーには多様な価値観があり、誰1人としてまったく同じ考えの方はいないでしょう。
そのなかでも評価され上位表示されている記事があります。
上位表示される記事の特徴を調べ、どんなユーザーか想定しながらSEO記事を作成しましょう。